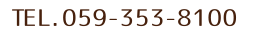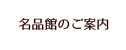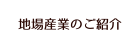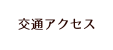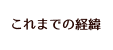いらこ(煎粉)

- 主な商品
- おこし・あられ・フライ菓子の原料
- 始まり
- 明確でない
- 由来
- 農業などの副業として生産加工をおこなっていました。
- 主な生産地
- 四日市市天カ須賀
いらこの歴史
菓子種(かしだね)として「おこし」、「あられ」や「フライ菓子」 の原料であり、創業の時期は明確でないが、大正末期には四日市市の天ヵ須賀(あまがすか)を中心に周辺地区にかけて150戸が、 農業などの副業として生産加工をおこなっていました。
当時の製法は米をせいろで蒸して、 塩水に浸し、ふくらまして、再度、蒸して天日乾燥させるという作業で、一定量の米をいかに多量にふくらませ、 美しく見ばえよく乾燥させるかの技術の優劣が商売のポイントでした。
天ヵ須賀地域では天日乾燥の手段として浜風や鈴鹿おろしが吹き、 そのふくらませる技術として海水に浸す方法が研究され、 海水使用により安価でなおかつ同じ量の原料米で多量に生産できるという有利性がありました。 その点から天ヵ須賀の業者が優位にたち他地区の業者は廃業していきました。
戦時中は食料事情の悪化により全て生産がなくなりましたが、 戦後は再開され、原料や製品の転換しながら、事業の機械化と拡大化が図られ、原料も米から小麦粉、 澱粉(でんぷん)に代わりました。